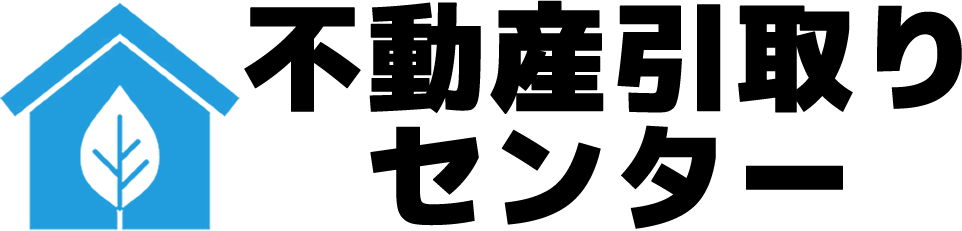売れない家を抱えていると、持ち続けることが思わぬ負担になることがあります。固定資産税や維持費用、修繕費などがかかり続けるだけでなく、家が老朽化すれば周囲とのトラブルや次世代への負担を避けられなくなることもあります。
そんな「売れない家」をどうすればいいのか悩んでいる方に向けて、この記事では、家が売れにくい理由や放置することで生じるデメリット、そして実際に家を手放すための具体的な方法について詳しく解説します。
相続放棄や国庫帰属制度の利用、市町村への寄付や無償譲渡など、さまざまな手段を検討し、売却が難しい不動産の負担を軽減するためのヒントを提供します。適切な方法を選択することで、不動産の維持にかかる手間とコストを減らし、安心して次のステップに進むことができるでしょう。
売れない家の特徴
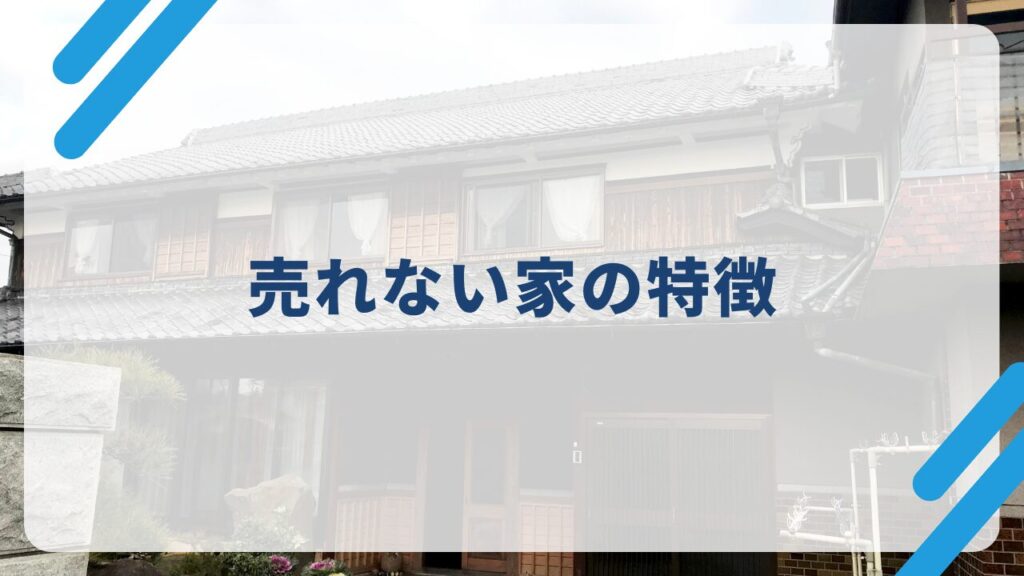
売れない家にはさまざまな特徴がありますが、共通しているのは価格、立地、建物の状態などが原因であることです。以下では、それぞれの特徴について詳しく見ていきます。
価格設定が高すぎる
家が売れない理由の一つは、価格設定が相場よりも高すぎることです。不動産市場では、同じエリアや類似の条件を持つ物件が他に存在し、それらと比較して価格が高い場合、買い手はその物件に見向きしなくなります。多くの売主は、自分の家に高い価値を感じるため、相場よりも高い価格をつける傾向がありますが、これが売れ残りの大きな原因となります。
例えば、同じエリアで築50年の住宅が300万円で売り出されている中、築60年で特にリフォームもされていない家を600万円で売り出した場合、買い手は当然少しでも新しい方の物件に魅力を感じるでしょう。価格設定を適切に行うためには、不動産会社に相談し、地域の相場を正確に把握することが重要です。結論として、価格設定は売却成功の鍵であり、相場を考慮して現実的な価格をつけることが必要です。
需要が無い立地
立地条件も、売れない家の大きな原因の一つです。都市部や交通の便が良い場所に比べ、田舎や過疎地にある家は、そもそも買い手が少ないことが問題です。また、駅や商業施設から遠い、または周辺に生活インフラが整っていない地域では、住宅の需要が低く、結果として売れにくい状況が生まれます。
例えば、駅からバスで30分以上かかるような郊外の物件や、スーパーや病院が近くにない場所では、特にファミリー層の需要がほとんどないため、売却が難しくなります。こうした場合、価格を大幅に下げるか、空き家を利用したビジネスとしての活用を検討する必要が出てきます。結論として、立地条件は物件の売却成功に大きく影響し、需要の少ない地域では工夫が必要です。
建物自体に欠陥がある
建物自体に欠陥がある場合も、売れない家の一つの特徴です。例えば、築年数が古く、耐震基準を満たしていない物件や、水回りの設備が老朽化している物件などは、買い手にとって大きなマイナス要素となります。特に耐震性や断熱性に問題がある家は、修繕に大きな費用がかかるため、購入をためらう買い手が多いのです。
具体例として、築30年以上の物件は特に売却が難しく、耐震補強工事を行わなければ売りにくいことが多いです。また、購入者がリフォームを前提に考えている場合でも、修繕費が予想以上にかかるとわかれば、その物件の購入を避ける傾向があります。こうした場合、先に売主がリフォームや修繕を行うか、買い手にその費用を考慮した価格で売り出すことが解決策となります。結論として、建物に欠陥がある場合は、修繕やリフォームを検討し、適切な対応を取ることが重要です。
売れない家を放置するデメリット
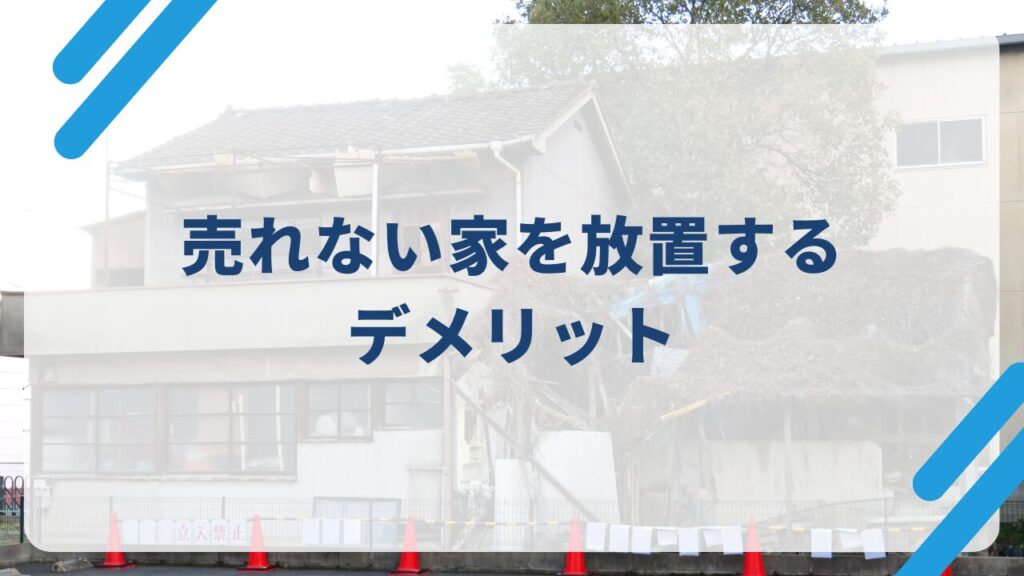
家が売れないからといって放置しておくと、さまざまなデメリットが生じます。固定資産税の増額や近隣住民とのトラブル、次世代への負担など、放置することによるリスクを無視するわけにはいきません。以下、具体的なデメリットについて詳しく解説します。
維持費がかかる
家を放置しておくと、維持費が増加してしまう点が最大のデメリットです。まず、固定資産税は家が建っている限り課されますが、放置された空き家は「特定空き家」に指定されると、税金の軽減措置が外され、固定資産税が最大6倍に跳ね上がる可能性があります。また、老朽化が進むと修繕費用もかさむため、空き家の維持は多大なコストを伴うことになります。
例えば、木造家屋の場合は築22年が耐用年数とされており、それを超えると建物自体の価値はほとんどなくなります。放置期間が長ければ長いほど資産価値は下がり、修繕が必要な箇所も増えていくため、売却も難しくなります。結論として、放置することで維持費が増大するため、早めの対策が重要です。
近隣からのクレームになる場合も
空き家を放置しておくと、周囲の住民からクレームが入るリスクも高まります。特に、建物が老朽化して外壁が崩れるなどの危険がある場合や、雑草が生い茂って害虫が発生する場合などは、近隣の環境に悪影響を及ぼします。また、不法投棄や不審者の侵入など、治安の悪化を招く可能性もあります。
このような問題が発生した場合、行政から空き家の所有者に管理指導が行われ、最悪の場合は強制撤去や罰金を課せられることもあります。結論として、空き家の放置は近隣トラブルを引き起こすリスクがあるため、適切な管理が求められます。
次世代も負担を相続する
家を放置すると、その負担は次世代にも引き継がれます。家や土地の所有権が相続されると、相続人は固定資産税や管理義務を負うことになりますが、売却や活用が難しい物件の場合、次世代がこの負担を引き受けざるを得ない状況に陥ります。
相続放棄が可能な場合もありますが、他の財産も放棄しなければならないため、慎重な判断が必要です。また、放置された家が「特定空き家」に指定されてしまうと、固定資産税の増加や行政代執行による解体費用の請求など、さらなる負担を次世代が抱えることになります。結論として、家を放置して次世代に負担を先送りすることは避けるべきです。
売れない家を手放す方法

売れない家や土地を持ち続けると、管理費や固定資産税など多くのコストがかかり、負担が増えていきます。ここでは、そんな不動産を手放すための方法を4つ紹介します。
①相続放棄する
相続放棄は、相続した家や土地を引き継がずに済む方法の一つです。相続放棄を行うことで、相続人はその家の所有権を放棄し、管理義務や固定資産税などの負担もなくなります。ただし、相続放棄を選択すると、その他の財産もすべて放棄することになるため、預金や貴重品などを含むすべての遺産を受け取れません。また、相続放棄の申請には期限があり、相続開始後3ヶ月以内に家庭裁判所に申述しなければならないため、早めの決断が必要です。結論として、相続放棄は土地や家の負担を避ける手段として有効ですが、他の財産も失うリスクがあるため慎重に検討すべきです。
②国庫帰属制度を利用する
2023年に施行された「相続土地国庫帰属制度」を利用すれば、相続した土地を国に引き渡すことが可能です。これにより、土地の所有や管理から解放され、固定資産税の負担もなくなります。ただし、この制度にはいくつかの条件があり、建物が建っていないことや土地の境界が明確であることなどが求められます。さらに、国に引き取ってもらうには、管理費として10年分の標準的な費用を支払う必要があるため、完全に無料で手放せるわけではありません。結論として、国庫帰属制度は条件を満たせば有効な手段ですが、費用がかかる点を事前に理解しておく必要があります。
③市町村へ寄付
市町村への寄付も、土地や家を手放す方法の一つです。寄付を受け入れてもらえれば、管理や維持の負担がなくなり、将来的な負担を避けられます。しかし、寄付が成立するにはその土地が地域社会にとって有益である必要があり、受け入れられるケースは限られています。例えば、公園の敷地拡張や地域の公共施設として活用できる土地であれば、市町村が寄付を受け入れることがありますが、売れ残っているような土地の場合、寄付が難しいこともあります。結論として、市町村への寄付は有効な手段ではあるものの、実際に受け入れてもらえるかは地域のニーズに依存します。
④無償譲渡・引取りサービスを検討
無償譲渡や引取りサービスは、売却が難しい不動産を手放すための最後の手段として有効です。無償譲渡は、家や土地を無料で他人に譲り渡す方法で、相続人や近隣住民、さらには企業や個人投資家に譲渡することが考えられます。引取りサービスでは、特定の条件を満たす不動産を引き取ってもらえることがありますが、建物が老朽化している場合や、維持費がかかりすぎる土地は拒否されることもあります。結論として、無償譲渡や引取りサービスは、売却が難しい不動産を手放すための選択肢の一つですが、譲渡先を見つけるために積極的な活動が必要です。
結論:売れない家を手放す方法について

売れない家を手放す方法には、いくつかの有効な手段があります。まず、相続放棄を利用すれば、負担を引き継がずに済みますが、他の財産もすべて放棄することになるため慎重な判断が必要です。また、国庫帰属制度を利用して土地を国に引き渡すことができる場合もありますが、条件を満たす必要があり、コストもかかることを考慮する必要があります。さらに、市町村への寄付や無償譲渡などの選択肢も検討する価値がありますが、受け入れられるかどうかは土地の状態や地域のニーズ次第です。いずれにしても、売れない家を持ち続けることはコストや管理の負担を増大させるため、早めに手放すための計画を立てることが重要です。専門家に相談しながら、自分に最適な解決策を見つけることで、将来的な負担を軽減することができます。